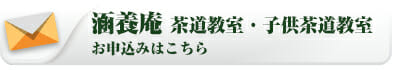11月は炉開きの月、茶人のお正月と言われている月です。緊急事態宣言も解除され、コロナも落ち着いているので、本当にしばらくぶりに涵養庵でのお茶の稽古にしました。

準備の時には、一瞬炭を考えましたが、やはり電気ヒーターの炉壇をすえました。炉縁は紫檀のものにしました。そして飾り壺の置き方を先生にお聞きして床の間に飾りました。飾り壺拝見を参加の方々がそれぞれ行いました。

涵養庵の露地入り口にある鉢のもみじの葉はカサカサになってしまいました。黄色いツワブキの花が咲いています。庭には梅と花海堂の枯葉が落ちて、これらは石に張り付いて始末が大変です。庭の枯葉を取ったり、雑草を抜いたりしてお迎えました。今年は苔が良くならなかったです。土、砂を撒いたり、噴霧装置を設置したりしたのですが、復活しませんでした。
今回は子供たちも涵養庵でのお稽古にしました。炉開きの様子を見て、それを学んでもらおうという珠乃先生のご意向です。そして、客としての所作を、通してお稽古しました。
涵養庵でお茶を飲むことが出来ることが本当にうれしいです。
| お道具 | |
|---|---|
| 軸 | 「日日是好日」 |
| お茶碗 | 大樋焼 長左衛門 萩焼 坂田泥華 赤楽 和楽 七五三 信楽焼 一陶 |
| 水差し | 瀬戸焼 一重口 |
| 薄茶器 | 棗 堆朱、秀衡塗り |
| 茶銘 | 楽寿の昔、珠の白 柳櫻園 |
| 釜 | 阿弥陀釜 |
| 炉縁 | 紫檀 大工の製作 |
| 建水 | 曲げ物木地 |
| 花入れ | 備前 掛け花入れ |
| 花 | 白椿、水引 |
| 食籠 | 有田焼 |
| 主菓子 | 亥の子餅 |
| 干菓子 | もみじ、かきね 木富 |
涵養庵でのお稽古はどこか雰囲気が違います。落ち着きます。
今回も、密を避けるために、窓を開放しましたが、小春日和で寒くなくお稽古ができたのは、年配者にとってはありがたかったです。外の雑音も気にならない程度でした。
以前に聞いた時には、子供たちにとって、涵養庵は暗すぎと感じたようでした。今回は涵養庵でのお稽古を楽しんだようです。少しお茶を学んできて茶室を含めて楽しむことが分かってきたのかもしれないと思いました。子供たちにお茶の楽しさを教えるのは珠乃先生も本当にうれしそうでした。この子たちがここでのご縁をきっかけにして、末永く欲を言えば一生涯、茶道を楽しんでもらえるようになってもらえるように頑張ろうかと思います。
来月は師走。お稽古は、子供たちを含めて皆さんが涵養庵を望みました。12月9日にいたしました。(後日こちらのコラムも掲載予定です)コロナ禍が収まり、もっと涵養庵でお稽古がしたいものです。